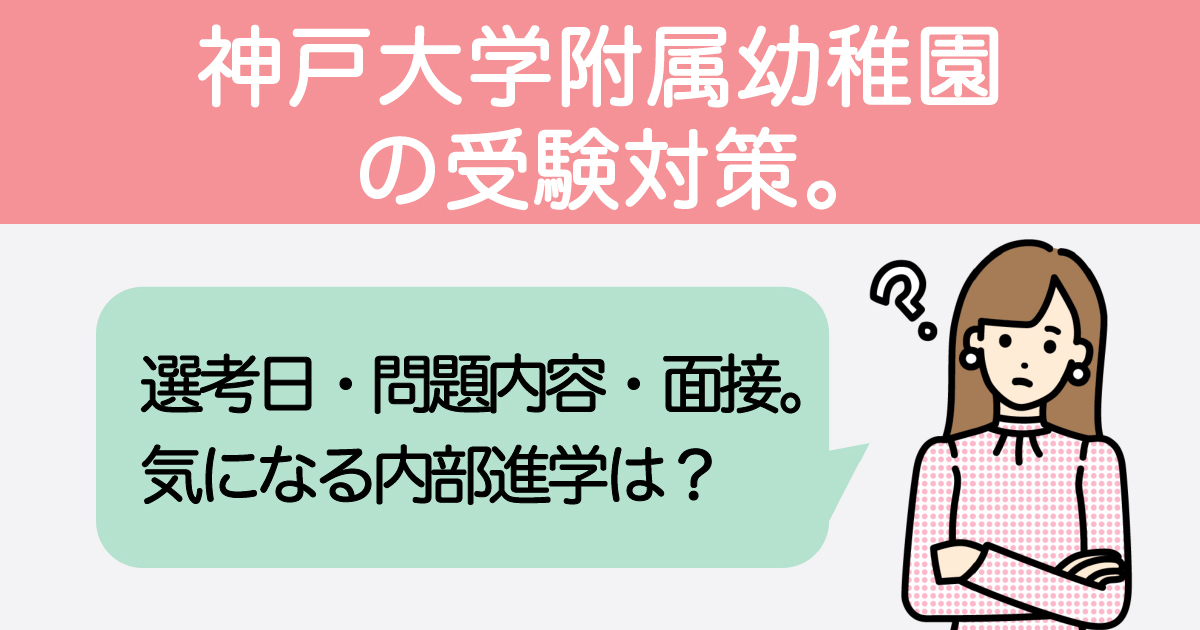「共働きでも合格できる?」
「どんな準備が必要?」
「倍率が高くて不安」
120年の研究歴史を誇る神戸大学附属幼稚園。
文部科学省研究開発学校として日本の幼児教育をリードする名門校の受験対策を、2026年度最新募集要項と実際の体験談で徹底解説します。
内部進学制度の詳細、自然体重視の試験実態、共働き家庭の具体的戦略が分かり、質の高い日常の子育てが合格への確実な道筋となるでしょう。
神戸大学附属幼稚園の特徴と価値
神戸大学附属幼稚園は、明治37年創立の120年を超える研究実績を持つ日本屈指の幼児教育機関です。
文部科学省研究開発学校指定校として、最先端の教育研究を行い、日本の幼児教育界をリードしています。
研究機関としての圧倒的実績
神戸大学附属幼稚園は単なる幼稚園ではなく、日本の幼児教育研究をリードする最高水準の研究機関です。
明治37年(1904年)の創立以来、120年以上にわたって幼児教育の発展に貢献してきました。
現在も文部科学省研究開発学校に指定され、幼稚園教育要領の改善や教育方法の開発を担っています。
「幼稚園教育要領における5領域の構成と要領上の用語の不一致が、小学校教師の幼児教育への理解を停滞させている一因と考える。そこで、領域の枠組みを資質・能力の観点から再編し、要領上の用語の整合性を図ることにより、幼小双方の教師の理解を促進し、幼小の接続を推進するカリキュラムと指導方法の研究開発を行う。」
引用:神戸大学附属幼稚園 令和6年度~9年度研究開発実施報告書
特にICT活用教育では、位置測位システムを活用した幼児理解の深化など最先端の研究を行っており、
お子様が通園すれば最新教育手法の恩恵を直接受けられます。
2026年度募集要項【最新】
令和8年度(2026年度)入園の募集は3年保育3歳児のみで、男女合わせて40名です。
募集要項配布は令和7年6月20日から開始され、対象は令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれの幼児となります。
重要な変更点として、平成28年度より2年保育4歳児の募集は完全に廃止されているため、入園を希望される場合は3歳児での受験が必須です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 募集人数 | 3年保育3歳児 男女40名 |
| 対象生年月日 | 令和4年4月2日~令和5年4月1日 |
| 要項配布 | 令和7年6月20日~ |
| 通園時間制限 | 40分以内(徒歩・公共交通機関利用) |
| 2年保育 | 平成28年度より募集停止 |
通園時間40分以内の条件は厳格に運用されており、明石駅から幼稚園までの徒歩7分を含めて計算されます。
事前に正確な所要時間を確認しておきましょう。
学費・費用(2025年度参考)
神戸大学附属幼稚園の学費は国立大学附属校として非常に良心的な設定です。
入園料31,200円と保育料73,200円(年額)は幼児教育無償化の対象となるため、実質的な負担はありません。
ただし、月額4,435円の諸費用(教材費・図書費・飲料費・育友会費)は保護者負担となります。
「入園料、保育料につきましては、幼児教育無償化の対象です。」
引用:神戸大学附属幼稚園 令和8年度園児募集要項
私立幼稚園と比較すると年間数十万円の差が生まれるため、経済的メリットは大きいといえます。
延長保育や預かり保育の制度がないため、共働き家庭では送迎体制の整備が課題となりますが、質の高い教育を受けられる環境として高い価値があります。
内部進学制度について|附属小学校への道筋

神戸大学附属幼稚園から神戸大学附属小学校への内部進学制度が設けられています。
外部受験とは異なる仕組みがあり、幼稚園での3年間が小学校進学への重要な準備期間となります。
制度の詳細を正確に理解して、戦略的に取り組みましょう。
内部進学制度の仕組み
神戸大学附属幼稚園から附属小学校への内部進学制度が設けられており、外部受験生とは別日程・別内容の試験が実施されます。
内部進学では最終段階での抽選がないため、外部受験と比較して確実性の面で大きなメリットがあります。
ただし、全園児が自動的に進学できるわけではなく、一定の基準を満たす必要があります。
具体的な進学者数や合格率は公表されていませんが、内部進学制度の存在により、幼稚園での3年間を小学校進学に向けた準備期間として活用できます。
園の教育方針である「自ら考え行動する力」を身につけられれば、内部進学だけでなく小学校入学後の学習にもスムーズに適応できるでしょう。
外部受験との違いと優位性
内部進学最大の優位性は、外部受験で実施される最終抽選がない点です。
外部受験では考査で優秀な成績を収めても、最終段階の抽選で不合格となる可能性があります。
一方、内部進学では日常の園生活を通じて評価され、抽選に左右されない確実な進学機会を得られます。
また、内部生は幼稚園での3年間で附属校の教育方針に慣れ親しんでいるため、小学校入学後の環境適応もスムーズです。
幼小連携教育の恩恵を最大限に受けられる点も、内部進学の大きな魅力といえます。
具体的な進学実績については園に直接お問い合わせいただくか、説明会での確認をお勧めします。
試験内容と攻略法|「準備より自然体」で臨む
神戸大学附属幼稚園の試験は、特別な技能や知識ではなく、年齢相応の発達と自然な姿勢を重視する傾向にあります。
過度な受験準備よりも、日常生活での健全な成長が評価のポイントとなるため、家庭での自然な子育ての延長として捉えましょう。
試験構成と基本的な流れ
神戸大学附属幼稚園の入園選考は、諸検査・面接・健康診断により合格者が決定されます。
国立大学附属幼稚園では一般的に、行動観察と面接が中心となり、お子様の自然な様子と家庭での教育環境が総合的に評価される傾向があります。
特別な能力測定ではなく、年齢相応の発達状況と基本的な生活習慣の確認が主な目的と推測されます。
園側は試験内容の詳細公表を控えているため、説明会での情報収集と、日常の自然な成長を重視した準備が合格への近道となります。
過去の受験体験談も参考になりますが、制度変更の可能性があるため、最新の説明会での情報確認が最も重要です。
行動観察で見られるポイント
国立大学附属幼稚園の行動観察では、お子様が他の子どもや先生と自然に関わる様子が評価される傾向にあります。
特別な技能よりも、自発性・協調性・集中力といった社会生活の基本的な力が重視されるため、普段の遊びや生活習慣の中で自然に身につく範囲で十分です。
おもちゃの取り合いをせずに順番を守れるか、新しい環境に興味を示せるかなど、年齢相応の社会性が確認されると推測されます。
日頃から公園や児童館で他の子どもと遊ぶ機会を増やし、集団生活への適応力を自然に育てておきましょう。
一つの遊びに5〜10分程度取り組める集中力も重要とされるため、
家庭では簡単なルールのある遊びや、絵本の読み聞かせを通じて持続的な注意力を育てておくと良いでしょう。
面接対策の核心
面接では保護者の教育方針と家庭環境、お子様の基本的な受け答え能力が確認されます。
志望理由については研究機関としての神戸大学附属幼稚園への理解が重要で、単なる進学メリットではなく教育理念への共感を具体的に示す必要があります。
共働き家庭の場合、送迎体制や行事参加の計画について質問される可能性があるため、家族の協力体制を明確に説明できる準備をしておきましょう。
- なぜ当園を志望したのか(研究機関への理解必須)
- お子さんの長所と課題は何か
- 家庭での教育で心がけている点
- 通園時間40分以内の条件への対応
お子様への面接では、名前・年齢・好きなものを緊張せずにはっきり答えられるかが基本となります。
練習しすぎて機械的にならないよう、日常会話の延長として自然な受け答えを心がけましょう。
運動能力・言語力・基本概念の確認内容
国立大学附属幼稚園では、年齢に応じた基本的な発達状況が確認される傾向にありますが、特別な技術や高度な能力は求められません。
運動面では歩く・走る・止まる・両足ジャンプなど、普段の公園遊びで身につく基本動作が中心です。
手先の器用さについては、クレヨンで丸を描く・シール貼り・簡単な積み木遊びなど、日常的な遊びの範囲で評価されます。
言語発達では自分の名前や好きなものを元気に話せれば十分で、数の概念では1から3までの数唱や「大きい・小さい」の区別程度が確認されます。
赤・青・黄の基本色識別や、丸・三角・四角の基本図形認識も見られる可能性がありますが、いずれも特別な訓練ではなく家庭での自然な関わりで身につけられる内容です。
重要なのは完璧な習得よりも、お子様なりの成長過程と取り組む姿勢です。
月齢差も考慮されるため、早生まれのお子様も焦らず年齢相応の発達を目指しましょう。
0〜3歳別準備ロードマップ|共働きでも間に合う戦略
幼稚園受験の準備は、お子様の年齢に応じた段階的なアプローチが重要です。
特別な早期教育ではなく、健全な成長を促す日常的な関わりが合格への基盤となります。
共働きのご家庭でも無理なく実践できる具体的な方法をご紹介します。
0〜1歳:生活リズムの基盤作り

- 早寝早起きの習慣化
- 親子のスキンシップ重視
- 絵本読み聞かせ1日1冊
- 規則正しい食事時間
0〜1歳では規則正しい生活習慣の土台づくりが最優先です。
早寝早起きのリズムを整え、授乳や離乳食の時間を一定にすれば、集団生活への適応力が自然に身につきます。
親子のスキンシップを大切にし、たくさん話しかけながら愛着関係を深めてください。
絵本の読み聞かせは言語発達の土台となるため、1日1冊を目標に継続しましょう。
共働きのご家庭では、朝と夜の15分間を濃密な親子時間として確保すれば十分な準備ができます。
保育園を利用している場合、園での集団生活経験が社会性の発達に役立つため、家庭では愛情深い関わりに集中できます。
1〜2歳:社会性の芽生え期

1〜2歳は挨拶や返事の習慣を日常に取り入れる重要な時期です。
他の子どもや大人との関わりを大切にし、公園や児童館での交流機会を積極的に作ってください。
食事ではスプーンやフォークの正しい持ち方と姿勢を身につけ、トイレトレーニングを段階的に始めれば自立心を育めます。
手先の器用さを養うため、積み木遊びやシール貼りを取り入れるのが効果的です。言葉の数を50〜100語程度、二語文が出始めるよう、日常会話を意識的に増やしましょう。
失敗を恐れず、お子様のペースに合わせて進めるのを心がけてください。
母子分離の準備も段階的に始める時期です。まず家庭内で短時間から始め、祖父母宅や一時保育を活用して分離時間を少しずつ延ばしていきます。
2〜3歳:受験直前仕上げ期
2〜3歳では他の子どもと一緒に遊べる力を重点的に育てましょう。
公園や児童館で積極的に他の子どもと関わる機会を作り、自分の名前と年齢をはっきり言える練習を継続してください。
運動面では走る・跳ぶ・ボールを投げるといった基本動作を覚え、クレヨンやシール貼りなどの簡単な作業で手先の動きを上達させます。
この時期は一つの活動に集中して取り組む時間を少しずつ延ばし、集中力と持続力を自然に身につけられるよう配慮しましょう。
早生まれのお子様は月齢差を意識し、焦らずお子様のペースに合わせて進めるのを心がけてください。
- 集団での遊び体験
- 名前・年齢の明確な発話
- 基本運動能力の向上
- 簡単な作業への集中力
着替え・歯磨き・片付けなどの生活習慣を自分でできるよう練習し、
「必ずお迎えに来る」約束を守りながら母子分離の時間を段階的に延ばしていきます。
共働き家庭の時間管理術
- 朝夕各15分の集中親子時間
- 移動時間の有効活用
- 日常生活の学習機会化
- 家族全体の協力体制構築
共働きのご家庭では朝15分・夕方15分の親子遊び時間確保を目標にしてください。
夫婦でそれぞれの得意分野を担当し、協力体制を作りましょう。
一時保育やファミリーサポートを母子分離練習を兼ねて積極的に活用するのをおすすめします。
車での移動中に教育音楽を流したり、日常の料理や買い物を学習機会に変えたりする工夫を取り入れてみてください。
祖父母や親族に協力をお願いし、家族全体でサポート体制を整えれば、無理なく受験準備を進められるでしょう。
重要なのは量より質で、短時間でも集中した関わりを持てれば十分な効果が期待できます。
受験前の重要な疑問に答えます

神戸大学附属幼稚園受験を検討する保護者の方から寄せられる代表的な不安や疑問にお答えします。特に共働き家庭での合格可能性や高倍率への対処法、通園条件について、現実的な視点で解説いたします。
Q1: 共働きでも合格できますか?
共働き家庭でも十分に合格可能です。
現在では共働き家庭への理解が深まっており、適切な準備と送迎体制があれば問題ありません。
重要なのは確実な送迎体制の構築で、ファミリーサポートやシッター、祖父母との協力を組み合わせて対応策を準備しましょう。
面接では具体的な送迎計画と行事参加方法を明確に説明できるよう準備してください。
延長保育がないため勤務時間の調整が必要ですが、共働きで培われたお子様の自立心や社会性がプラス評価される場合も多く、限られた時間での質の高い親子関係が評価につながります。
Q2: 倍率の高さは心配すべき?
倍率の高さに過度に不安を感じる必要はありません。
神戸大学附属幼稚園では考査後に抽選が実施されるため、基本的な準備ができていれば誰にでも合格の可能性があります。
特別な技能や知識は求められず、年齢に応じた自然な成長が最も重視されるため、日常的な子育ての充実が最良の対策となります。
結果以上に価値があるのは、家族で目標に向かって努力した経験です。
重要なのは園の教育方針への理解と共感で、研究機関としての使命を理解できるかが長期的な満足度を左右します。
Q3: 通園時間40分は厳格ですか?
通園時間40分以内の条件は非常に厳格に運用されています。
明石駅から幼稚園までの徒歩7分を含めて計算されるため、自宅から最寄り駅までの時間も慎重に検討する必要があります。
神戸市玉津町など周辺地域からの通園実績もありますが、事前に正確な所要時間を測定しておきましょう。
公共交通機関の遅延リスクも考慮し、余裕を持った通園計画を立てるのが重要です。
入園後に通園区域外へ転居した場合は退園となるため、長期的な居住計画も含めて検討してください。
申請時には通園所要時間証明書の提出が求められます。
Q4: 併願戦略はどうすればいい?
併願は可能ですが、選考日程の重複を避ける点が最も重要です。
各園の特色を理解した上で、優先順位を明確にしましょう。
国立は抽選要素があり運に左右される面が強く、私立は実力重視の傾向が見られます。
願書提出や面接日が重ならないよう事前確認が必須で、幼稚園によっては併願を認めていない場合があるため募集要項の詳細確認を怠らないでください。
費用と時間管理も重要な要素となり、検定料・交通費・準備時間を効率的に配分し、第一志望を明確にした上で無理のない範囲での併願戦略を立てるのをお勧めします。
願書・志望理由書の準備ポイント

願書と志望理由書は合格への重要な要素です。
園の教育方針への理解と家庭の価値観の一致を明確に示し、具体的なエピソードで説得力を高めましょう。
研究機関としての特徴を踏まえた協力姿勢も欠かせません。
園の教育方針と家庭の価値観の一致点を明確に示す方法
志望理由では園の教育理念への深い理解と共感を具体的に表現しましょう。
ホームページや説明会で園の「真摯・自由・協同」の精神や、子どもの自主性を重視する方針を確認し、ご家庭の教育観との接点を見つけてください。
単なる進学メリットではなく、「人間らしくよりよく生きるための行動の基盤を幼児自らに形成させる」教育目標への賛同を示すのが重要です。
説明会や見学会での体験談を盛り込むと、園への理解と熱意が伝わりやすくなります。
抽象的な表現ではなく、園の具体的な取り組みに対する感想や期待を織り交ぜて記述しましょう。
具体的なエピソードで家庭の取り組みを伝える書き方
お子様の個性を魅力的に伝えるため、長所と課題の両面を成長エピソードと共に説明しましょう。
客観的な分析力を示しながら、お子様の魅力を肯定的に表現してください。
日常生活での具体的な場面を挙げて、どのような場面でお子様の成長を感じたか、どのような働きかけを行ったかを詳述します。
例えば「公園で年下の子に譲る姿を見て思いやりの心を感じた」「失敗しても諦めずに挑戦する姿勢を大切に育てている」など、園が重視する自主性や協調性につながる具体例を選びましょう。
家庭での教育方針も、実際の体験談と結びつけて説明すると説得力が増します。
国立附属園の特徴を理解し協力姿勢を示す表現方法
教育実習生の受け入れや研究活動への協力姿勢を明記しましょう。
神戸大学附属幼稚園は研究機関として、幼児教育の発展に貢献する使命を担っています。
この役割を理解し、研究協力や教育実習への積極的な参加意思を表明してください。
「教育研究の発展に微力ながら貢献したい」「将来の教師育成にお役に立ちたい」といった具体的な協力意思を示します。
また、園の研究成果を家庭教育にも活かしたい前向きな姿勢を伝えると効果的です。
120年の研究歴史や文部科学省研究開発学校としての価値を理解している旨も盛り込みましょう。
文章作成時の注意点と最終チェック項目
誤字脱字の確認、適切な敬語の使用、読みやすさを心がけます。
完成後は声に出して読み返し、自然な文章かどうか最終チェックしましょう。
一文の長さが適切か、同じ語尾が連続していないかも確認してください。
専門用語を使う場合は簡潔な説明を加え、読み手の立場に立った分かりやすい表現を心がけます。
提出前には家族にも読んでもらい、客観的な意見を求めるのをお勧めします。
園の募集要項で指定された文字数や形式を守り、期限に余裕を持って完成させてください。
真摯で誠実な姿勢が文章全体から伝わるよう意識しましょう。
家庭でできる学習準備と学習習慣の作り方

お子様が楽しみながら続けられる環境作りが基本です。
特別な教材がなくても、日々の暮らしの中にたくさんの学びがあります。
短時間でも質の高い関わりを重視しましょう。
日常生活を活用した自然な学習機会の創出
料理のお手伝いで数の概念を、お買い物で社会性を、散歩で観察力を育てられます。
「にんじん3本取って」「赤いりんごはどれ?」など、日常会話に学習要素を自然に織り込みましょう。
お風呂での数唱、洗濯物たたみでの色や形の確認、食事での「大きい・小さい」の比較など、特別な時間を設けなくても学習機会は豊富にあります。
重要なのは親子で楽しみながら取り組める雰囲気作りで、勉強として意識させずに自然な体験として提供してください。
失敗を恐れず、お子様の興味に合わせて柔軟に対応するのがポイントです。
読書習慣と言葉の力を伸ばす取り組み
単なる読み聞かせから、読後の対話を大切にする読書スタイルに変えてください。
読み終えた後に「どの場面が好きだった?」「どんな気持ちかな?」と話し合う習慣をつけると、言葉の力が伸びていきます。
お子様の反応に耳を傾け、想像力を働かせる質問を投げかけましょう。
図書館を積極的に活用し、様々なジャンルの絵本に触れる機会を作ってください。
読書は知識だけでなく、集中力や想像力、語彙力を総合的に育てる最良の方法です。
毎日の継続が重要ですが、時間より質を重視し、親子で楽しめる読書時間を大切にしましょう。
知育教材の選び方と効果的な活用法
知育教材を選ぶ時は、年齢に適しているか・続けられるか・親子で楽しめるかを重視しましょう。
高価な教材より、お子様の興味と発達段階に合った内容が重要です。
例えば「モコモコゼミ」は小学校受験でも有名なこぐま会とSAPIXによる幼児向け教材で、受験対策に役立つとされています。
»こぐま会教材、提携SAPIX(サピックス)ピグマの「幼児通信教育モコモコゼミ」 ![]() の口コミはこちら
の口コミはこちら
ただし、教材に頼りすぎず、親子の関わりを中心とした学習スタイルを維持してください。
無料体験や資料請求を活用し、複数を比較してお子様に最適なものを選びましょう。
継続できる分量と内容で、楽しみながら取り組める環境を作れば、お子様の力が自然と伸びていきます。
集中力と持続力を育てる日常的な工夫
一つの活動に取り組む時間を少しずつ延ばしていけば、集中力と持続力が自然に身につきます。
最初は5分程度から始め、お子様の様子を見ながら段階的に時間を延ばしてください。
パズルやブロック遊び、お絵かきなど、お子様が夢中になれる活動を見つけるのが重要です。途中で飽きても無理強いせず、「今日は頑張ったね」と励ましながら終了しましょう。
テレビやスマートフォンなどの刺激を控えめにし、静かで集中しやすい環境を整えてください。
短時間でも毎日継続すれば、確実に集中力は向上します。
親も一緒に取り組む姿勢を見せると、お子様のやる気も高まります。
今すぐ始める3つのアクション

幼稚園受験の準備は、現在のお子様の状況把握から始まります。
適切な情報収集と計画的な取り組みで、合格に向けた道筋を明確にしましょう。
Step1: 年齢別チェックリストで現在地を確認
お子様の現在の発達状況を客観的に把握し、受験までの準備計画を立てましょう。
生活習慣・社会性・言語・運動の4領域で月齢に応じた発達目標と照らし合わせ、優先して取り組むべき課題を明確にしてください。
語彙数・基本運動・手先の器用さを年齢基準と比較し、強みと弱みを把握します。
優先して取り組む課題を絞り込み、最重要3項目を特定して具体的な改善計画を立てましょう。
限られた時間で効果的な準備を進めるため、焦点を絞った取り組みが合格につながります。
完璧を目指すより、お子様なりの成長過程を大切にしてください。
Step2: 説明会・見学会の申込み確保
園の雰囲気や教育方針を直接確認できる貴重な機会です。
令和7年度は6月9日(月)・6月21日(土)・11月22日(土)に開催予定で、今年度受験希望者は6月の回への参加が推奨されています。
先着順に受け付け、定員になり次第締め切られるため、公式ホームページの定期確認が欠かせません。
事前質問リストを用意し、当日はメモを取って後日整理する習慣をつけると効果的です。
教育方針の確認・施設環境・先生の対応を重点的にチェックし、お子様の園への反応も判断材料として活用しましょう。
他の保護者との情報交換も良い機会となります。
Step3: 継続的な情報収集と準備体制の構築
受験情報は日々変化するため、継続的な情報収集体制の構築が欠かせません。
公式情報を定期的に確認し、募集要項・選考方法・日程変更にすぐ対応できるよう準備しておきます。
信頼できる情報源として、公式発表・教育専門誌・実績ある幼児教室からの情報を重視し、口コミや噂に惑わされないよう注意してください。
家族全体のサポート体制を整え、年間スケジュール・重要日程・準備進捗を記録する専用ノートを活用すると効果的です。
夫婦の役割分担を明確にし、祖父母や親族の協力も含めた総合的な準備計画を立てましょう。
まとめ
神戸大学附属幼稚園受験では、特別な早期教育より年齢相応の自然な成長が最も重要です。
120年の研究実績を持つ名門校として、お子様の自発性や協調性を日常生活で育てる家庭が評価されます。
共働き家庭でも適切な送迎体制があれば合格可能で、0歳からの段階的な準備ロードマップに沿って進めれば十分対応できるでしょう。
まずは6月の説明会申込みと最新募集要項の確認から始め、家族全員で質の高い日常の子育てに取り組んでください。
過去問を書籍で入手する

幼児教室や通信教育教材を使えば、プロのカリキュラムで知育教育ができ、便利です。
例えば、「ベビーパーク(神戸市・芦屋市・西宮市・川西市・明石市・姫路市)」では0歳2ヶ月から、
「mikihouseの幼児教室(神戸市)」では0歳10ヶ月から、
「ドラキッズ(神戸市・尼崎市・西宮市)」では満1歳から、成長に合わせたプログラムが用意されています。
チャイルド・アイズのような受験対策塾に入る前のプレ教室として利用している方も多いです。

また、「こどもちゃれんじBaby(0歳~)」のような通信教育も、親子で一緒に学べるスタイルで楽しめます。
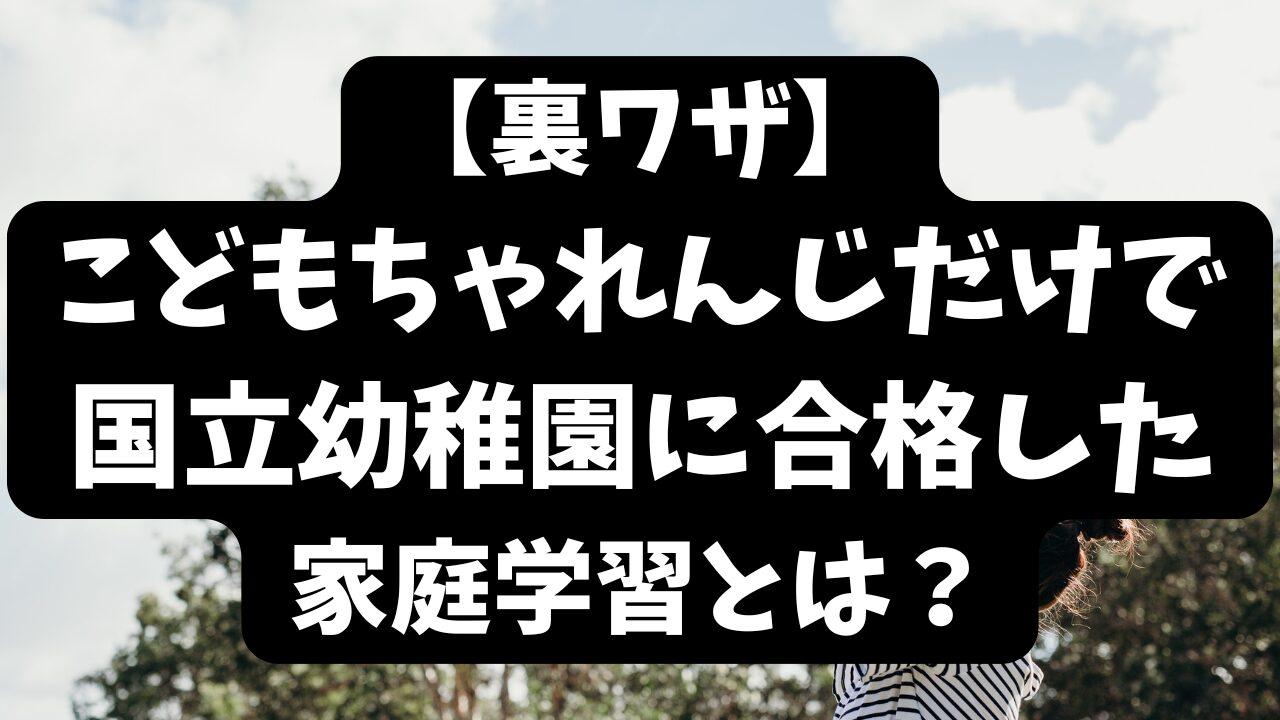
最後に、受験対応の通信教育を利用して、お子様の学びを仕上げましょう。
「モコモコゼミ」のような受験特化型の教材は、試験対策に必要な内容が詰まっています。
教材の無料お試し体験を利用し、お子様が楽しく学べる環境を整えてあげましょう。
»こぐま会教材、提携SAPIX(サピックス)ピグマの「幼児通信教育モコモコゼミ」 ![]() の口コミはこちら
の口コミはこちら


幼児教育は「早ければ早いほど良い」と言われる一方で、
「どの教室を選べばいいのか?」
「本当に効果があるのか?」
「料金に見合う価値があるのか?」
と、不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか?
特に国立大附属幼稚園受験を考えているご家庭では、
「ただ通わせるだけで良いのか?」
「受験対策として適切な内容なのか?」
と、慎重に判断する必要があります。
そこで、 “0歳2ヶ月から通える” 教室を選択肢に加えてみませんか?
実際に通った家庭の 「体験談」 をもとに、
早期教育の 「メリット・デメリット」 を詳しく解説しています。
未来の選択を後悔しないために、まずは【無料でできること】から始めてみましょう!