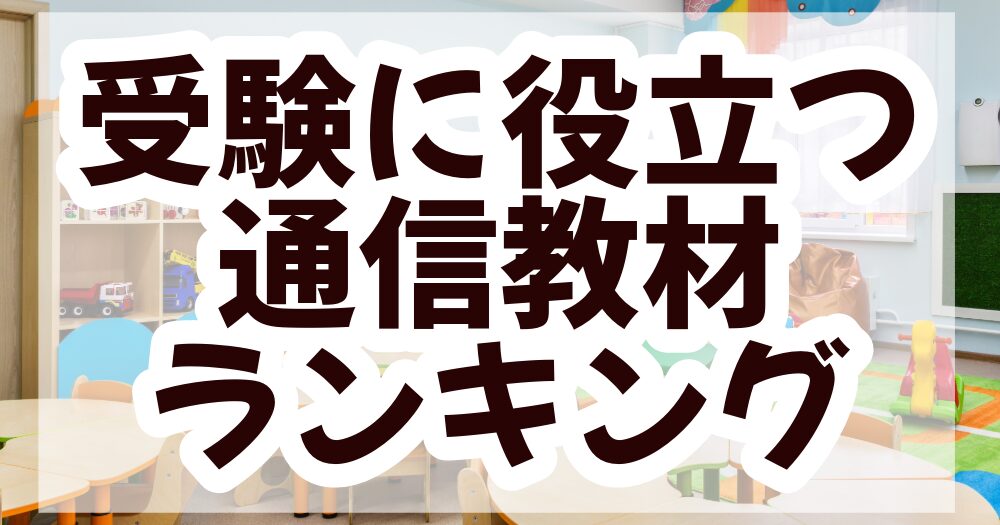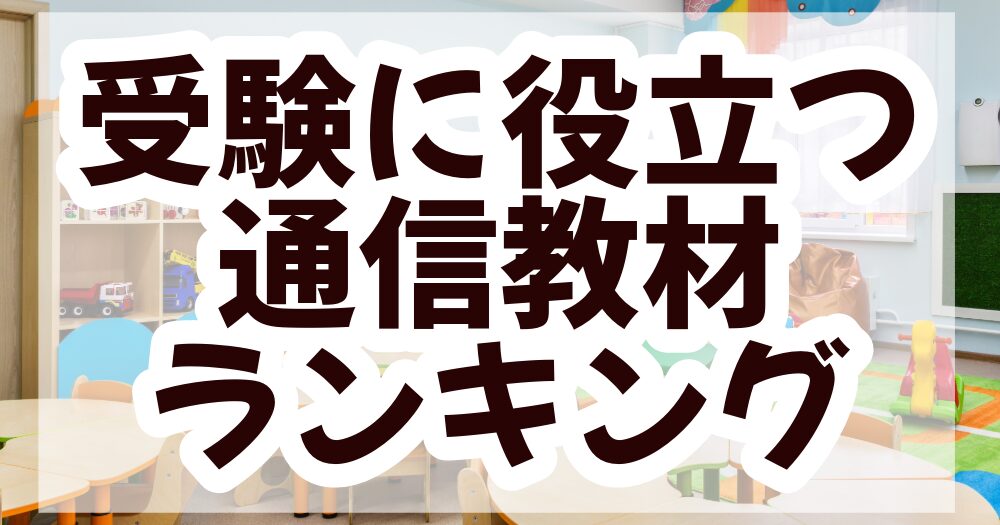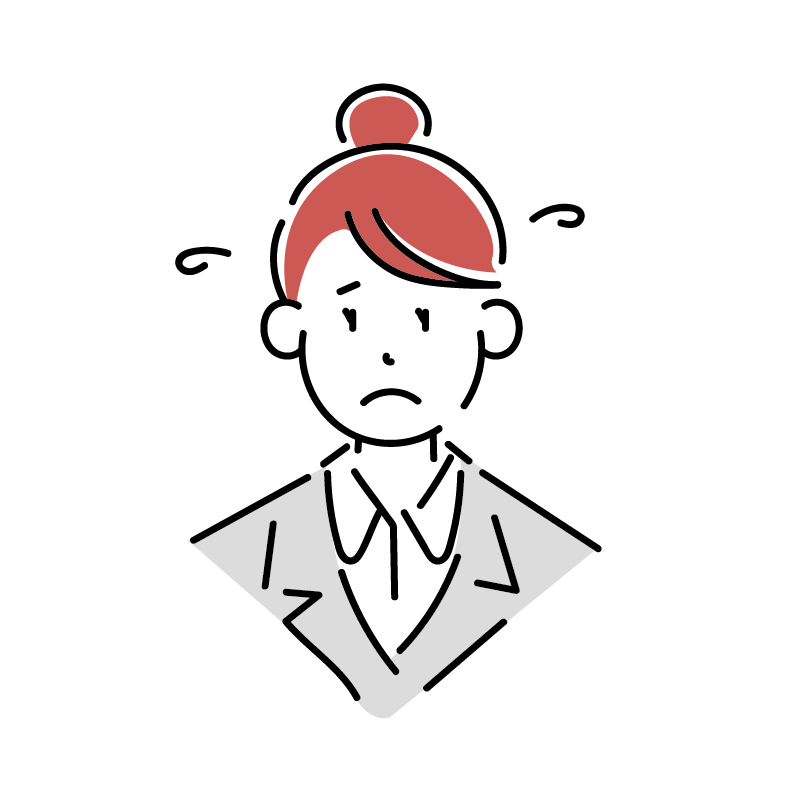 困ったママ
困ったママ「弘前で国立幼稚園を目指すなんて、無謀でしょうか?」
先日、弘前市内のママ友からそんな相談を受けました。都市部と違って情報が圧倒的に少ない弘前で、しかも青森県で唯一の国立幼稚園。ネットで検索しても出てくるのは関東の情報ばかりで、「片道1時間以内の通園区域って、具体的にうちは入るの?」「預かり保育がないって聞いたけど、共働きは本当に無理?」といった切実な疑問への答えが見つからない。
そんな中、近所の先輩ママから「もう準備始めてる?うちは1歳から幼児教室通わせてるよ」なんて言われて、急に焦り始める。でも弘前には選択肢が限られているし、何が正解なのか分からない。「都市部みたいに情報がないから、もう諦めた方がいいのかな…」そう思い始めている保護者も多いのではないでしょうか。


実は私も2021年から幼稚園受験サイトを運営する中で、弘前の保護者からの相談が特に多いことに気づきました。元小学生家庭教師として、また二児の母として実際に受験を経験した立場から言えば、情報が少ないからこそ、正しい情報と適切な準備方法を知ることで、都市部の家庭よりも有利になれる可能性すらあります。
この記事では、令和8年度の最新募集要項をもとに、弘前大学教育学部附属幼稚園の「本当のところ」をお伝えします。通園区域の実際の境界線、共働き家庭が知っておくべき現実的な対応策、そして地方だからこそできる効率的な準備方法まで。読み終わる頃には「情報がないから不安」だった気持ちが「やるべきことが明確で、むしろ有利かも」に変わっているはずです。
弘前大学教育学部附属幼稚園の基本情報と最新受験データ
「青森で唯一の国立幼稚園って、やっぱり特別なの?」そんな疑問を持つ保護者も多いでしょう。弘前大学教育学部附属幼稚園は確かに特別な存在です。令和8年度の募集要項が正式公表され、詳細な選考スケジュールも判明しました。ここでしか得られない最新情報をお伝えします。
2025年度の選考日程・募集人数・倍率動向
「いつ、何人募集で、どれくらい競争が激しいの?」気になる基本データが確定しました。
- 3歳児 30名
- 4歳児 20名程度
数字を見て「やっぱり狭き門…」と感じる方もいるかもしれません。でも実際の競争相手は「弘前から片道1時間以内に住んでいる家庭」に限られているため、都市部ほどの激戦ではありません。
- 出願書類受付 9月2日(火)~19日(金)
- 入園願書交付 9月24日(水)~10月3日(金)※29日除く
- 選考日 10月16日(木)
- 合格発表 10月21日(火)14時30分
手続き時間は平日の午前9時30分~午後4時30分のみ。共働き家庭には「有給取らないと手続きできない」現実があります。検定料1,600円も受検者本人名義での振込が必須で、細かなルールに注意が必要です。
出典 弘前大学教育学部附属幼稚園「令和8年度園児募集要項」
https://home.hirosaki-u.ac.jp/youchien/
正確な倍率は非公表ですが、青森県内で選択肢が限られているだけに、確実に人気は高まっています。
考査内容と合格に必要な3つの評価項目
「うちの子、何ができれば合格できるの?」答えが令和8年度の選考内容に隠されています。
選考は「行動観察(運動と遊び等)と親子面接及び健康診断等」。一見シンプルですが、内容には深い意味があります。
集団での「普通」が一番大切 行動観察で見られるのは、おもちゃの貸し借り、順番待ち、先生の簡単な指示理解など。「特別にできる子」より「みんなと仲良く遊べる子」が求められています。弘前の子どもたちは比較的のんびりしているので、都市部の過度な競争意識は不要でしょう。
親子面接は「ありのまま」で勝負 志望理由と家庭での関わり方が中心です。「なぜ弘前で唯一の国立幼稚園を選んだのか」「共働きなのに大丈夫なの?」といった質問にも、素直に答えられる準備をしておきましょう。
年齢相応の発達があれば十分 名前が言える、基本的な運動ができる、簡単な絵が描ける程度で問題ありません。都市部の幼児教室で鍛えられた子と競う必要はなく、弘前らしいゆったりとした成長で十分対応できます。
内部進学の実績と小学校受験への影響
「附属幼稚園に入れば、小学校受験しなくていいの?」多くの保護者が気になる核心部分です。
公式には「幼稚園から小学校、中学校への滑らかな接続により子ども一人ひとりの成長と発達を見守っています」と案内されており、実際に多くの園児が附属小学校に進学しています。弘前では小学校受験の選択肢が限られる中、附属小学校への道が開けているのは大きなメリットでしょう。
ただし「全員自動進学」ではありません。具体的な進学率や選考基準は非公表のため、入園後に詳しい説明があると考えておいた方が安心です。万が一、他の小学校を受験する場合でも心配いりません。自由保育で培われた主体性や考える力は、どの学校でも評価される基盤となります。
弘前から県外の私立小学校を受験する家庭も、附属幼稚園での経験は必ずプラスになるはずです。何より、幼児期の貴重な時間を小学校受験の準備に追われず、のびのびと過ごせるのは、子どもにとって最高の環境といえます。
過去問題で分かる出題傾向と対策方法
「過去問ってあるの?どんな準備をすればいいの?」弘前の保護者が困る情報不足を解決します。
弘前大学教育学部附属幼稚園では過去問の公式発表はありません。でも心配無用です。選考内容から準備の方向性ははっきりと見えてきます。年齢に応じた基本的な成長確認が中心で、都市部の幼児教室で行われる高度な課題は出ません。普段の公園遊びや家族との時間を大切にするだけで、十分に対応できる内容です。
市販では「受験専門サクセス 弘前大学附属幼稚園 受験 問題集」が参考になりますが、完璧に同じ問題が出るわけではありません。どちらかといえば「園がどんな力を求めているか」を知るための参考書として活用してください。
特におすすめしたいのはチューリップクラブへの参加です。年7回開催される園の体験事業で、実際の雰囲気を肌で感じられます。他の受験予定家庭との情報交換も可能で、弘前ならではの「顔の見える関係」が築けるかもしれません。参加申込みは2週間前からなので、早めにスケジュールをチェックしておきましょう。
過去問に振り回されるより、日常生活での親子の関わりを大切にした準備こそが、弘前大学教育学部附属幼稚園が求める子どもの姿に近づく最適な方法です。
年齢別受験対策ロードマップ 3つの準備ステップ
「いつから何を始めればいいの?」「早すぎても遅すぎても心配…」そんな不安を抱える弘前の保護者も多いでしょう。
弘前大学教育学部附属幼稚園が目指す「自ら考え、自律的に行動できる子の育成」を意識しながら、お子さんの成長に合わせた無理のない準備方法をご紹介します。共働きの家庭でも実践できる内容です。
ステップ1 土台作りの時期(0歳〜1歳)「愛着形成と基本的信頼感」の構築


「0歳から受験準備なんて早すぎる?」いえ、大切なのは『お勉強』ではなく親子の絆です。
生活リズムを整えるところから始めましょう。早寝早起き、授乳や離乳食の時間を一定にすれば、自然と規則正しい習慣が身につきます。たくさん話しかけ、スキンシップを大切にして、親子の愛着関係を深めてください。絵本の読み聞かせは1日1冊を目標に続けていくと、言葉の発達にもつながります。
共働き家庭では「時間がない」と感じるかもしれませんが、朝と夜に15分ずつでも濃密な時間を過ごせれば十分です。お子さんのペースを大切にして、焦らず見守ってあげてください。
ご家庭で遊びの延長で豊かな刺激を与えたい家庭には「こどもちゃれんじ」があります。
ただし、まずは日常の関わりを大切にしましょう。弘前では選択肢が限られているからこそ、親子の時間が何より価値のある準備になります。
ステップ2 社会性の芽生え(1歳〜2歳前半)「生活習慣と他者との関わり」を育む時期


「周りの子と比べて遅れてない?」弘前の子育てはゆったりペースで大丈夫です。
「おはよう」「ありがとう」の挨拶や、「はい」のお返事を日常に取り入れましょう。スプーンやフォークの使い方、トイレトレーニングも少しずつ始めて、自分でできる範囲を広げていきます。積み木やシール貼りで手先を使い、語彙を50〜100語、二語文でのおしゃべりを目標に会話を楽しんでください。
弘前で家庭学習を考えるなら「モコモコゼミ」がおすすめです。小学校受験で実績のあるこぐま会とSAPIXが作った教材で、遊び感覚で考える力を伸ばせます。地方でも自宅で質の高い学習内容に触れられるのが魅力です。
失敗しても大丈夫。都市部の競争に巻き込まれず、お子さんのペースに合わせて楽しく続けていけばいいのです。弘前らしいゆったりとした子育てが、実は附属幼稚園の求める「自主性」につながります。
ステップ3 受験準備期(2歳後半〜)「集団行動と指示理解」の仕上げ期


「いよいよ本格的な準備?」でも特別な訓練は必要ありません。
他の子どもと一緒に遊べるよう、弘前市内の公園や子育て支援センターで積極的に交流する機会を作ってください。自分の名前と年齢をはっきり言える練習も忘れずに。走る、跳ぶ、ボール投げなどの基本的な運動や、クレヨンでのお絵かき、シール貼りで手先の動きを練習しましょう。
早生まれのお子さんは、月齢差を気にせずマイペースで進めてください。お子さんの成長スピードに合わせるのが一番です。弘前の子どもたちは比較的のんびり育っているので、都市部の子どもと比較して焦る必要はありません。
家庭だけでは限界もあります。特に集団での様子は家では分からないため、専門の幼児教室やプレ保育の利用も検討してみてください。ステップ1・2でしっかり土台ができていれば、集団の中でも自然に力を発揮できるはずです。
弘前という環境だからこそ、競争に追われず、お子さんらしい成長を大切にした準備ができます。それが結果的に、附属幼稚園が求める「自ら考える子」につながるのです。
出典 弘前大学教育学部附属幼稚園「令和8年度園児募集要項」
https://home.hirosaki-u.ac.jp/youchien/
面接・行動観察で差がつく!当日までの実践準備
「面接で何を聞かれるの?」「行動観察って何を見られるの?」保護者が最も不安に感じる選考当日の様子について、具体的にお答えします。弘前大学教育学部附属幼稚園の選考は、お子さんの日常をありのままに見る内容です。特別な訓練は不要で、年齢相応の発達と基本的な生活習慣があれば十分対応できます。
面接で問われる家庭の教育方針と答え方
「青森県で唯一の国立幼稚園を選ぶ家庭って、どんな教育方針なの?」面接官も気になる部分です。
よくある質問は「どうして弘前大学教育学部附属幼稚園を選んだのか」「お子さんの良いところと心配なところ」「家庭で大切にしていることは何か」など。模範解答を暗記するのではなく、日頃の子育てで実際に心がけている内容を素直に話せるよう準備してください。
園が目指す「自ら考え、自律的に行動できる子の育成」に関連して、家庭でどんな関わりをしているか聞かれるかもしれません。「考える時間を作る」「失敗も経験させる」など、具体的なエピソードとともに答えられると好印象でしょう。地方らしいゆったりとした子育て環境を活かした話ができれば、面接官にも伝わりやすいはずです。
共働きの場合は、送迎体制について質問される可能性があります。祖父母の協力やファミリーサポートの利用など、具体的な計画を説明できると安心です。国立大学附属園では教育実習生の受け入れもあるため、研究活動への協力についても前向きな姿勢を伝えましょう。
行動観察テストで評価される子どもの特徴
「うちの子、他の子とうまく遊べるかな?」保護者が心配する集団での様子が見られます。
令和8年度は「行動観察(運動と遊び等)」が実施され、他の子どもとどのように関わるかを中心に観察されます。おもちゃの貸し借りができるか、順番を守って遊べるか、先生の簡単な指示を理解できるかなど、基本的な内容です。新しい環境でも興味を持って遊びに参加できるか、ひとつの活動に5〜10分程度集中して取り組めるかも確認されます。
家庭での準備は難しく考える必要がありません。弘前市内の公園で他の子どもと遊ぶ機会を作り、「貸して」「どうぞ」の言葉を使えるよう練習してください。家では簡単なルールがある遊び(じゃんけんやかくれんぼなど)を楽しみながら、ルールを守る習慣を身につけましょう。
自分の名前と年齢をはっきり言える練習も忘れずに。緊張していても答えられるよう、日頃から人に会ったときの挨拶を習慣にしておくと安心です。この地域の子どもたちは人見知りする子も多いので、無理をせずお子さんのペースで慣れていけば大丈夫です。
共働き家庭が気をつけるべき準備の現実
「預かり保育なしで共働き、本当に大丈夫?」共働き家庭が直面する現実的な課題があります。
弘前大学教育学部附属幼稚園は預かり保育を実施していないため、フルタイム勤務の継続には工夫が必要です。時間が限られている中でも、朝夕15分ずつでも濃密な親子時間を作ればいいのです。車での移動中に歌を歌ったり、お買い物で数を数えたり、日常生活の中にも学びの機会はたくさんあります。
送迎体制については早めの準備が必要です。弘前では祖父母が近くに住んでいる家庭も多いので、まずは家族の協力体制を検討してみてください。ファミリーサポートやシッターサービスなど、複数の選択肢を準備しておきましょう。面接では具体的な送迎プランを説明できるよう、事前に家族で話し合っておくのが大切です。
一時保育やファミリーサポートは、受験準備の母子分離練習としても活用できます。お子さんが慣れるまでに時間がかかる場合もあるため、早めに利用を始めてみてください。
働いているからこそお子さんの自立心が育っている面もあります。共働きである状況を負い目に感じず、家族の協力体制や子どもの成長を前向きにアピールする気持ちで面接に臨みましょう。弘前だからこそ実現できる、祖父母や地域との連携を活かした子育てを堂々と話せばいいのです。
出典 弘前大学教育学部附属幼稚園「令和8年度園児募集要項」
https://home.hirosaki-u.ac.jp/youchien/
教材・幼児教室の賢い選択法
「隣のママが『モコモコゼミ始めたの』って言ってたけど、うちも何かしなきゃダメなのかな?」
弘前での幼稚園受験準備では、選択肢が限られているからこそ家庭に合った方法を見つけるのが大切です。年齢に適した教材選択と継続可能な準備方法を考えてみましょう。無理をせず、親子で楽しめる範囲での取り組みが一番です。
家庭学習教材の効果的な活用方法
通信教材の最大のメリットは、弘前でも質の高い教育内容にアクセスできる点です。地方だからこそ、このメリットを活かしましょう。
2〜3歳の子どもには「お勉強」ではなく、遊びの延長として楽しめる教材を選んでください。「モコモコゼミ」は小学校受験で実績のあるこぐま会とSAPIXが作った教材で、カードやパズルを使いながら考える力を育てます。弘前大学教育学部附属幼稚園が目指す「自ら考える子」の土台作りにも適しています。
一方で「こどもちゃれんじ」は年齢に応じた発達段階を丁寧にサポートし、日常生活の中で自然に学べる構成です。どちらも自宅で取り組めるため、共働き家庭でも朝夕の短時間で続けられるのが魅力でしょう。
継続するコツは、お子さんが機嫌の良い時間帯を見つけて、短時間でも毎日触れることです。成果を急がず、親子のコミュニケーション手段として活用してください。週3回でも十分効果があります。
幼児教室選びで失敗しないポイント
弘前市内では幼児教室の選択肢が限られているため、体験授業での見極めが特に重要になります。
まず確認したいのは、お子さんの月齢に適した内容かどうかです。同じ3歳でも早生まれと4月生まれでは発達に差があるため、個別のフォローがあるかチェックしましょう。先生がお子さんの名前を覚えて声をかけてくれるなど、温かい雰囲気も大切な要素です。
弘前大学教育学部附属幼稚園の通園区域内で通いやすい立地かも判断材料になります。月謝以外の費用(教材費や発表会費用など)も事前に確認しておくと安心です。何より大切なのは、お子さんが楽しそうに参加できるかどうかです。
無理やり座らされているような教室では、受験準備以前に勉強嫌いになってしまう可能性があります。体験授業では、お子さんの表情をよく観察してください。
費用対効果を考えた投資優先順位
限られた予算の中で効果的な準備を進めるには、まず低コストで始められるものから試してみるのがおすすめです。
最初に取り組みたいのは過去問の確認です。市販の問題集で出題傾向を把握し、日常の遊びに活かしましょう。数千円の投資で準備の方向性が見えてきます。チューリップクラブへの参加も費用対効果の高い選択肢です。年7回開催される園の体験事業で、実際の雰囲気を感じられます。
給食試食会でも400円程度の参加費で、お子さんの園生活への適応度も確認できます。通信教材か幼児教室かで迷ったら、まず通信教材から始めてみてください。お子さんの反応を見てから幼児教室を検討しても遅くありません。
両方同時に始める必要はなく、段階的に検討すれば無駄な出費を避けられます。身近な材料での工作や弘前公園での自然観察など、お金をかけない学習機会も大切にしてください。
出典 弘前大学教育学部附属幼稚園「チューリップクラブ」
https://home.hirosaki-u.ac.jp/youchien/
よくある不安と疑問 弘前大学附属幼稚園受験Q&A
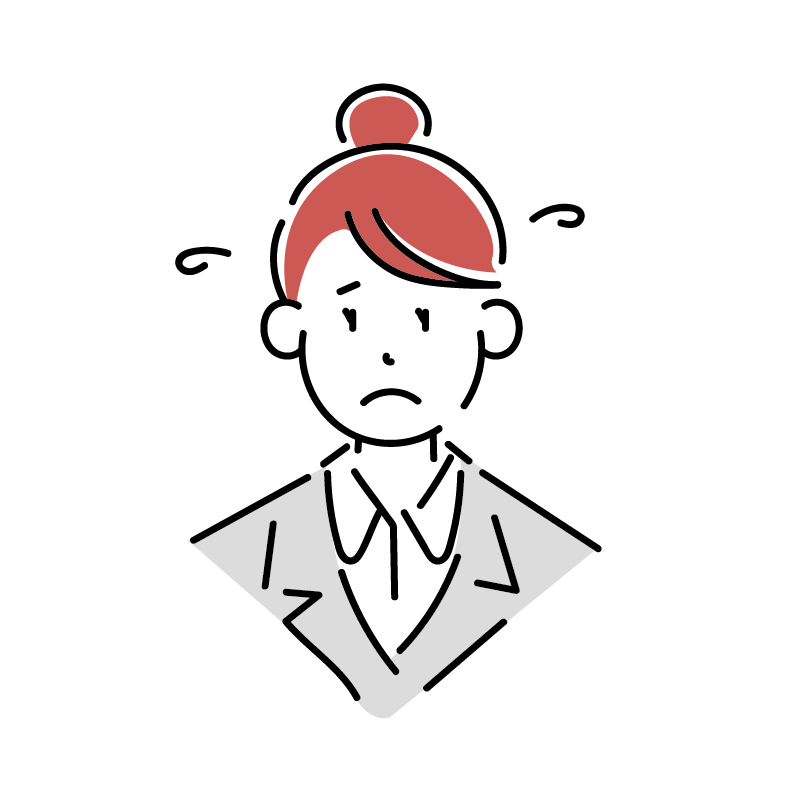
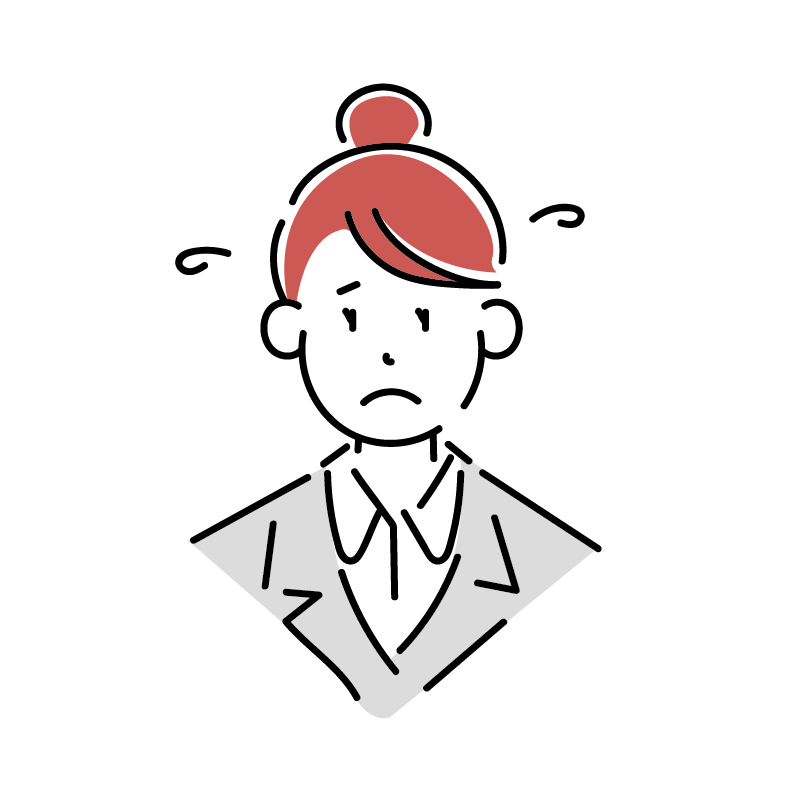
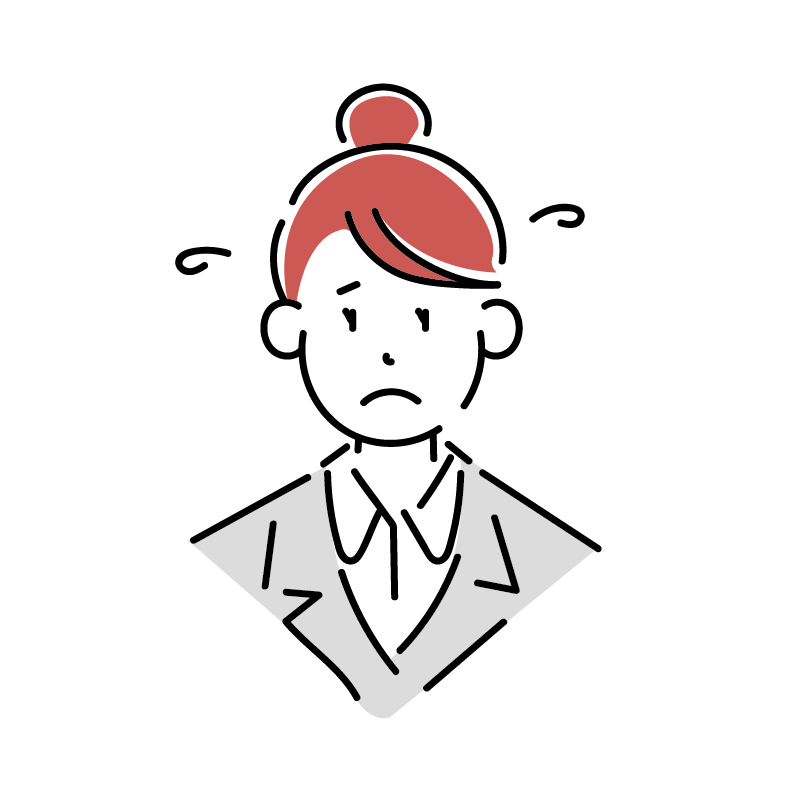
「ママ友との会話で不安になったんだけど、みんなはどうしてるの?」「うちだけ出遅れてない?」
弘前大学教育学部附属幼稚園を検討する保護者から寄せられる代表的な疑問にお答えします。
「2〜3歳に受験準備は早すぎる?」適正な開始時期
「まだ2歳なのに、もう準備した方がいいのかな?」そんな不安を感じているお母さんも多いでしょう。
2〜3歳からの受験準備は決して早すぎません。ただし、詰め込み式の学習は全く必要ありません。弘前大学教育学部附属幼稚園が目指す「自ら考え、自律的に行動できる子の育成」を考えると、年齢相応の自然な発達を促すアプローチが最も効果的です。
0〜1歳では親子の愛着関係と基本的な生活リズムの確立、1〜2歳では挨拶や生活習慣の定着、2〜3歳では他の子どもとの関わりと基本的な受け答えができれば十分対応できます。特別な教材や高度な知識は求められていません。
日常生活での親子の関わり、弘前公園での自由な遊び、絵本の読み聞かせなど、普通の子育ての延長で身につく力が評価の中心となります。早期からの準備は「特別な訓練」ではなく、「豊かな日常生活の積み重ね」と考えてください。



先輩ママの経験談
「早生まれで心配だったけど、焦らずマイペースで見守りました。子どものペースを大切にして正解でした」
「働きながらでも対策できる?」時間効率的な準備法
「フルタイムで働いてるけど、本当に大丈夫?」共働き家庭の最大の心配事ですよね。
働きながらでも対策は可能ですが、弘前大学教育学部附属幼稚園特有の制約を理解しておく必要があります。最大の課題は預かり保育が実施されていない点です。フルタイム勤務を継続するには、祖父母・親族のサポート、ファミリーサポートやシッター活用、職場での休暇調整が必須となります。
面接では送迎体制について具体的な計画を説明できるよう、事前準備が必要です。受験対策自体は限られた時間でも十分可能です。朝夕15分ずつの濃密な親子時間を確保し、車での移動中に歌を歌う、買い物で数を数えるなど、日常生活を学習機会に変える工夫を取り入れてください。
夫婦で役割分担をして、得意な分野を担当するのも効率的です。チューリップクラブなどの園体験事業への参加も、事前に日程を確認して有給休暇を調整すれば参加できます。



共働きママのアドバイス
「働いているからこそ培われる子どもの自立心を、面接では前向きにアピールしました」
費用はどのくらい?」受験にかかる総額目安
「お金がどれくらいかかるのか心配…」家計への影響も気になりますよね。
受験にかかる直接費用は比較的抑えられますが、準備期間中の教材費や通学後の送迎コストも考慮が必要です。
- 入園検定料 1,600円(令和8年度、返還不可)
- 健康診断書作成費 3,000〜5,000円程度
- 交通費 通園区域内での移動費
- 市販問題集 3,000〜5,000円程度
- 通信教材 月額2,000〜4,000円程度(利用する場合)
- 幼児教室 月額8,000〜15,000円程度(利用する場合)
- チューリップクラブ参加費 給食試食会で400円程度
国立幼稚園のため幼児教育無償化の対象となり、保育料の負担は軽減されます。ただし給食費や教材費などの実費は発生する可能性があります。預かり保育が利用できないため、共働き家庭ではシッターやファミリーサポートの費用(時給800〜1,200円程度)も検討が必要です。
総額では月額1〜3万円程度で準備可能ですが、家庭の状況に応じて調整してください。無理のない範囲で計画を立てましょう。
出典 弘前大学教育学部附属幼稚園「令和8年度園児募集要項」
https://home.hirosaki-u.ac.jp/youchien/
まとめ
「情報が少なくて不安だった」気持ちが「やるべき準備が見えてきた」に変わりましたか?弘前大学教育学部附属幼稚園の受験は、年齢に応じた段階的な準備で十分対応できます。
令和8年度の募集要項が確定し、選考は行動観察と親子面接が中心となります。0〜1歳では親子の愛着関係、1〜2歳では基本的な生活習慣、2歳後半からは集団での関わりを育てれば準備完了です。
預かり保育未実施のため共働き家庭には送迎体制の工夫が必要ですが、日常の親子時間を大切にした関わりで合格に近づけます。
チューリップクラブへの参加や市販問題集での傾向把握から始めて、お子さんのペースに合わせて進めてください。弘前だからこそできる、競争に追われない豊かな準備で、親子にとって最適な教育環境を手に入れましょう。
過去問を書籍で入手する
参考過去記事
「受験準備何から始める?」
「共働きでも大丈夫?」
「通園できる範囲は?」
弘前大学教育学部附属幼稚園の受験を検討する保護者が抱く不安は尽きません。
令和8年度募集要項の最新情報をもとに、通園区域制限や預かり保育未実施などの厳しい制約、自由保育の魅力と内部進学制度、年齢別の効果的な準備方法を詳しく解説。
計画的な対策で、お子さんにとって最適な教育環境への道筋が明確になります。
\直前でも自宅で対策OK!/
- 通園区域は片道1時間以内に限定、預かり保育未実施で共働き家庭には高いハードル。
- 合否のカギは〈生活習慣〉〈母子分離〉〈家庭の教育姿勢〉。
- 年齢別準備ロードマップで今すぐ確認を。
0〜3歳別ロードマップ|共働きでも間に合う受験準備
弘前大学教育学部附属幼稚園の受験準備は、子どもの年齢に応じた段階的なアプローチが大切です。
共働きのご家庭でも無理なく進められる具体的な準備方法をご紹介します。
0〜1歳の準備ポイント


生活リズムの安定が、すべての基盤になります。
0〜1歳では、規則正しい生活習慣の土台を築くのが最優先です。
早寝早起きのリズムを整え、授乳や離乳食の時間を一定にしましょう。
集団生活への適応力が自然に身につきます。
親子のスキンシップを大切にし、たくさん話しかけながら愛着関係を深めてください。
絵本の読み聞かせは言語発達の土台となるため、1日1冊は継続するよう心がけましょう。
共働きのご家庭では、朝と夜の15分間を濃密な親子時間として確保すれば、十分な準備ができます。
1〜2歳の準備ポイント


社会性の芽生えと基本的な生活習慣の確立に重点を置きます。
1〜2歳では、あいさつや「はい」の返事を生活に組み込み、スプーン・フォークの持ち方や段階的トイレトレで自立心を育てます。
積み木やシール貼りで指先を鍛え、語彙を50〜100語、二語文を目標に会話を増やしましょう。
家庭学習には、幼児からの受験指導で定評ある小学校受験塾こぐま会と中学受験塾SAPIXが共同監修した1歳用の通信教材「モコモコゼミ」プチコースがおすすめです。カードやパズルを遊び感覚で解きながら思考力を伸ばせ、地域を問わず難関校対策のノウハウを自宅で取り入れられます。
失敗を恐れず、お子さまのペースを尊重して継続してください。
2〜3歳の準備ポイント


集団での行動と基本的な受け答えが身につく時期です。
2〜3歳では、他の子どもと一緒に遊べる力を育てましょう。
公園や児童館で積極的に他の子どもと関わる機会を作ってください。
自分の名前と年齢をはっきり言える練習を忘れずに行います。
運動面では、走る・跳ぶ・ボールを投げるといった基本動作を覚えます。
クレヨンやシール貼りなどの簡単な作業を取り入れれば、手先の動きが上達するでしょう。
早生まれのお子さんは月齢差を意識し、焦らずお子さんのペースに合わせて進めるのを心がけてください。
母子分離と生活習慣の準備


母子分離の成功は段階的な慣らしがポイントです。
段階的な分離練習で、お子さんが安心して一人で過ごせる力を育てます。
母子分離は幼稚園受験で大切な準備の一つです。
まず家庭内で短時間から始め、祖父母宅、一時保育、幼児教室と段階的に分離時間を延ばします。
「必ずお迎えに来る」約束を守り、戻った時はしっかり褒めてあげてください。
同時に、着替え・歯磨き・片付けなどの生活習慣を自分でできるよう練習しましょう。
一つの活動に集中して取り組む時間を少しずつ延ばせば、集中力と持続力が自然に身につくはずです。
共働き家庭の時間管理術
朝と夕方の短時間を活用すれば、働きながらでも十分な準備ができます。
共働きのご家庭では、朝15分・夕方15分の親子遊び時間確保を目標にしてください。
夫婦でそれぞれの得意分野を担当し、協力体制を作りましょう。
一時保育やファミリーサポートを母子分離練習を兼ねて積極的に活用するのをおすすめします。
車での移動中に教育音楽を流したり、日常の料理や買い物を学習機会に変えたりする工夫を取り入れてみてください。
祖父母や親族に協力をお願いし、家族全体でサポート体制を整えれば、無理なく受験準備を進められるでしょう。
弘前大学教育学部附属幼稚園の特徴|教育方針・通園条件・募集要項
弘前大学教育学部附属幼稚園は、自由保育を重視した教育方針で注目を集める国立幼稚園です。
令和8年度募集要項が公表され、詳細な選考日程も確定しました。
教育方針と向いている家庭
幼稚園では、これまでの教育研究の成果を礎として、家庭や地域と連携しながら「自ら考え、自律的に行動できる子の育成」を目指し、遊びこむ子どもを育む保育を実践しています。
(出典:令和8年度弘前大学教育学部附属幼稚園募集要項)
子どもの自主性を尊重する自由保育が特徴で、一人ひとりの個性を大切にする家庭に適しています。
教育実習生の受け入れや研究活動への協力が求められるため、教育研究への理解がある家庭が望ましいでしょう。
附属小学校・中学校への連絡進学制度により、長期的な教育計画を立てたい家庭にもおすすめです。
通園エリア・アクセス
| 住所 | 〒036-8152青森県弘前市学園町1-1 |
| TEL | 0172-32-6815 |
| 公式サイト | https://home.hirosaki-u.ac.jp/youchien/ |
通園区域は厳格に制限されており、徒歩または交通手段で片道1時間以内の区域に限定されます(令和8年度募集要項)。
青森市については浪岡地区のみが対象となるため、事前確認が必要です。
保護者またはそれに準ずる人による送迎が必須条件となっており、公共交通機関の利用も認められています。
ただし、入園後に指定区域外へ転居した場合は退園となるため、転勤の可能性がある家庭は慎重な検討が求められます。
募集人数・抽選の有無・願書提出日程
令和8年度の募集人数と選考日程は以下の通りです。
| 年齢 | 募集人数 | 対象生年月日 |
| 3歳児 | 30名 | 令和4年4月2日~令和5年4月1日生 |
| 4歳児 | 20名程度 | 令和3年4月2日~令和4年4月1日生 |
| 5歳児 | 要問い合わせ | – |
- 出願書類受付:令和7年9月2日(火)~9月19日(金)
- 入園願書交付:令和7年9月24日(水)~10月3日(金)
- 選考日:令和7年10月16日(木)
- 合格発表:令和7年10月21日(火)14時30分
過去の倍率と人気の背景
具体的な過去の倍率データは公表されていませんが、募集人数30名に対して多くの応募が集まる人気園です。
人気の背景には、国立幼稚園としての質の高い教育、私立幼稚園と比較して経済的負担が軽いこと、附属小学校・中学校への連絡進学制度があります。
また、大正3年創設の長い歴史と実績、子どもの自主性を重視する教育方針が保護者からの支持を集めています。
令和7年度には「チューリップクラブ」の子育て支援事業も年7回実施されており、園体験の機会も充実しています。
費用・保育料・預かり保育の利用条件
入園検定料は1,600円(令和8年度募集要項)で、返還されません。
振込は受検者本人の名前で行う必要があります。
国立幼稚園のため、幼児教育・保育の無償化対象となり、保育料の経済的負担は軽減されます。
預かり保育は実施されていません。
弘前市の教育・保育施設一覧表で確認できるように、預かり保育の対象外となっています。
そのため、給食費や教材費などの実費負担は発生する可能性があります
\直前でも自宅で対策OK!/
試験内容と評価ポイント|行動観察・面接・家庭環境の見られ方
弘前大学教育学部附属幼稚園の選考は、お子さんの日常的な様子と家庭での教育環境を総合的に評価します。
特別な能力よりも、年齢相応の発達と基本的な生活習慣が重視されます。
行動観察で見られる力と伸ばし方
令和8年度の選考では「行動観察(運動と遊び等)」が実施されます。
他の子どもとの関わり方と、大人の指示への対応を中心に評価されるでしょう。
おもちゃを取り合わずに順番を守れるか、他の子どもと並行して遊べるかが確認されます。
自分から積極的に活動に参加する姿勢や、新しい遊びに興味を示す好奇心が大切です。
集中力については、一つの遊びに5〜10分程度取り組めるかをチェックします。
普段から公園や児童館で他の子どもと遊ぶ機会を増やし、家庭では簡単なルールのある遊びを取り入れてください。
親子面接で聞かれる質問と答え方のコツ
令和8年度の選考では「親子面接」が実施されます。
志望理由と家庭の教育方針について、具体的なエピソードを交えて答える準備をしましょう。
「なぜ当園を志望したのか」「お子さんの長所と課題は何か」「家庭での教育で心がけている点は何か」が中心になります。
抽象的な回答ではなく、日常生活での具体的な体験談を用意してください。
共働きの場合、送迎体制や行事参加の計画について質問される可能性があります。
家族の協力体制を具体的に説明できる準備をしておきましょう。
国立大学附属幼稚園の研究機関としての役割を理解し、教育研究への協力意志を明確に伝えるのをおすすめします。
子どもへの問いかけと自然な受け答え練習
名前・年齢・好きなものを、緊張せずにはっきり答えられる練習をします。
子どもへの面接では、基本的な受け答えができるかが確認されます。「お名前は何ですか」「何歳ですか」「好きな食べ物は何ですか」に、明瞭な声で答えられる練習をしましょう。
先生の簡単な指示(「赤いブロックを取ってください」など)を正確に理解し、行動できるかが評価されます。
「嬉しい」「困った」などの自分の気持ちを言葉で表現する練習を取り入れてください。
練習しすぎて機械的にならないよう、日常会話の延長として自然な受け答えを心がけていきましょう。
\直前でも自宅で対策OK!/
運動能力・言語力・数概念のテスト内容と対策
年齢に応じた基本的な成長を確認する課題で、特別な技術や能力は求められません。
令和8年度の選考では「運動と遊び等」の行動観察が行われます。
| 分野 (評価項目) | 確認される内容 (どんなテストがあるか) | 家庭での準備方法 (今からできること) |
|---|---|---|
| 基本運動 体を動かす力 | ・歩く・走る・止まる・両足ジャンプ ・ボール遊び・階段昇降 ・バランス感覚の確認 | ・公園での外遊びを増やす ・かけっこ・ボール遊びを楽しむ ・階段の昇り降り練習 |
| 手先の器用さ (巧緻性) | ・クレヨンで丸を描く・シール貼り ・積み木積み・ボタン操作 ・先生の真似をして形を作る | ・お絵かき・工作遊びを増やす ・ボタンのある服で練習 ・シール貼り・折り紙遊び |
| 言語発達 おしゃべりの力 | ・名前・年齢・好きなものを言う ・簡単な挨拶・返事 ・先生との簡単なやりとり | ・日常会話を増やす ・絵本の読み聞かせ ・挨拶の習慣づけ |
| 数の概念 かずや色の理解 | ・1〜3の数唱・大小の区別 ・基本色・基本図形の識別 ・色や形の名前を答える | ・数え歌・おもちゃの分類 ・色や形の名前を教える ・日常生活で数を意識する |
普段の親子遊びで十分伸ばせる力ばかりなので、焦らず毎日少しずつ練習していきましょう。
試験便利グッズ紹介
盲点かもしれませんが、考査(入試)が初めての方にぜひおすすめしたいのが、自立するA4バッグです。
長い待ち時間中もバッグが倒れる心配がないので、考査に集中でき、本当に重宝します。
上履きや水筒など、意外と荷物が増えるので、大きめで上品に見えるバッグが安心です。
願書・志望理由書の準備ポイント
園の教育方針と家庭の価値観の一致点を明確に示すのが大切です。
園の「自ら考え、自律的に行動できる子の育成」の教育目標と、家庭での取り組みとの関連性を具体的に記述しましょう。
チューリップクラブなどの園体験での印象を盛り込むと、園への理解と熱意が伝わります。
お子さんの個性を魅力的に伝えるため、長所と課題の両面を成長エピソードと共に説明しましょう。
客観的な分析力を示しながら、お子さんの魅力を肯定的に表現してください。
国立附属園の特徴を理解し、教育実習生の受け入れや研究活動への協力姿勢を明記するのも大切です。
家庭でできる準備と生活習慣の作り方
お子さんが楽しみながら続けられる環境作りが基本です。
短時間でも質の高い学習時間を確保しましょう。
特別な教材がなくても、日々の暮らしの中にたくさんの学びがあります。
料理のお手伝いで数の概念を、お買い物で社会性を、散歩で観察力を育てられるでしょう。
単なる読み聞かせから、読後の対話を大切にする読書スタイルに変えてみてください。
読み終えた後に「どの場面が好きだった?」「どんな気持ちかな?」と話し合う習慣をつけると、言葉の力が伸びていきます。
知育教材の選び方
年齢に適した教材選択で、無理なく楽しみながら学べる環境を整えましょう。
市販の知育教材を選ぶ際は、年齢適応性・継続可能性・親子で楽しめる内容を基準にしてください。
通信教育では、こどもちゃれんじ・モコモコゼミ・幼児ポピーなどがあり、それぞれ特徴が異なります。
例えば「モコモコゼミ」は小学校受験でも有名なこぐま会とSAPIXによる幼児向け教材で、受験対策に役立ちます。
≫モコモコゼミ詳細レビュー
詳しい教材比較は以下を参考にしてください。
≫幼児通信教育おすすめ比較
高額な教材に頼るよりも、身近な材料を使った工作や自然観察など、手作りの学習機会を大切にしてください。
教材選びで迷った時は、まず図書館や児童館の無料教材を試してから検討しましょう。
継続できる範囲で選択し、親子の時間を楽しむ心構えが一番大切です。


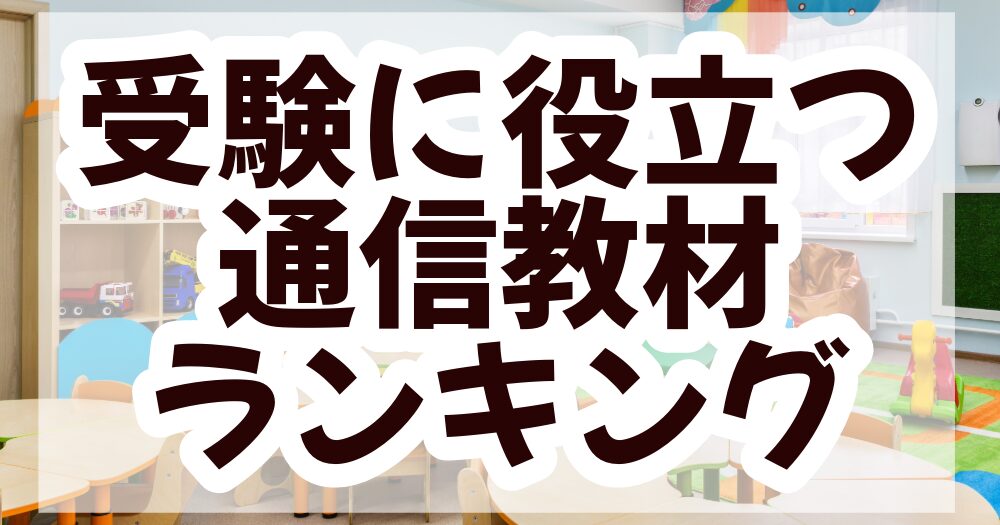
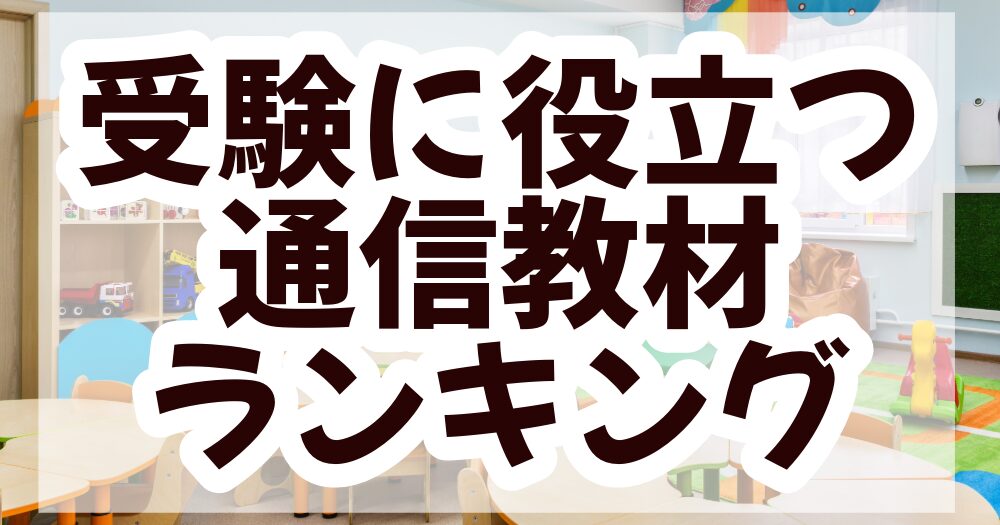
よくある不安にお答えします|共働き・倍率・併願戦略


弘前大学教育学部附属幼稚園を検討する保護者の方から寄せられる代表的な不安や疑問にお答えします。
特に通園区域制限や共働き家庭の対応について、具体的な事例とともに解説。
Q: 通園区域制限が厳しいと聞きました。どの範囲まで通園可能ですか?
徒歩または交通手段で片道1時間以内の区域に限定されます。令和8年度募集要項では、青森市は浪岡地区のみが対象と明記されています。
入園後に指定区域外へ転居した場合は退園となるため、事前の確認が欠かせません。
転勤の可能性がある家庭は、勤務先の人事異動方針を確認し、通園期間中の転居可能性を慎重に検討してください。
不明な場合は、具体的な住所を園に問い合わせて通園可能かを確認するのが確実です。
Q: 共働きでも合格できますか?
合格は可能ですが、かなり厳しい条件をクリアする必要があります。
平日午前9時30分〜午後4時30分の手続き時間、保護者送迎義務、預かり保育未実施などの制約があります。
夫婦の役割分担を明確にし、ファミリーサポートやシッター活用、祖父母との協力体制を事前に整えておきましょう。
職場への理解獲得と休暇調整も必須です。面接では送迎体制や行事参加の具体的な計画を説明できる準備をしてください。
共働きの経験がお子さんの自立心育成にプラスとなる側面もアピールできます。
Q: 入園後に転居する可能性があります。どう対応すればよいですか?
通園区域外への転居は退園となるため、慎重な検討が必要です。
令和8年度募集要項にも明記されている厳格なルールです。
転勤族の場合、在園期間中の人事異動可能性を勤務先に確認し、転居リスクを十分検討してから受験を決めましょう。
やむを得ず転居が決まった場合は、転居先の国立幼稚園への転園可能性もありますが、欠員状況により受け入れが困難な場合もあります。
事前に複数の選択肢を検討し、リスク管理を行うのが賢明です。
Q: 募集人数が少なく倍率が心配です。挑戦する価値はありますか?
挑戦する価値は十分にあります。
3歳児30名、4歳児20名程度の募集は確かに狭き門ですが、国立幼稚園の選考には運要素もあります。
年齢相応の発達と基本的な生活習慣が身についていれば、どのお子さんにもチャンスがあるでしょう。
特別な才能や高度な技術は求められておらず、日常の子育ての延長として準備を進められます。
家族全員で一つの目標に向かって過ごした時間は、結果にかかわらず貴重な経験となります。
着実な準備を進めれば、堂々と受験に臨めるはずです。
Q: 私立幼稚園との併願はできますか?
併願は可能ですが、日程調整と優先順位の明確化が必須です。
令和8年度の選考日は10月16日(木)に確定しているため、私立幼稚園の選考日と重複しないよう事前確認が必要です。
各園の教育方針の違いを理解し、面接での一貫性を保つ準備をしましょう。
併願する場合は、検定料・交通費・準備時間を効率的に配分し、第一志望を明確にした上で無理のない範囲での戦略を立ててください。
合格後の入学手続きスケジュールも把握しておくと、最終判断がスムーズになります。
Q: 預かり保育は利用できますか?
預かり保育は実施されていません。(令和7年度現在)
共働き家庭の場合、お迎え時間に合わせた勤務調整や、ファミリーサポート・シッターサービスの活用が必要になります。
祖父母や親族からのサポート体制を事前に整えておきましょう。
保育時間は通常の幼稚園と同様のため、フルタイム勤務の継続を希望される場合は、お迎え体制の確保が最優先課題となります。
\直前でも自宅で対策OK!/
その他のよくある質問
内部進学について|附属小学校への道筋


弘前大学教育学部附属学校園では、幼稚園から小学校、中学校への滑らかな接続により子ども一人ひとりの成長と発達を見守っています。
(出典:令和8年度弘前大学教育学部附属幼稚園募集要項)
弘前大学教育学部附属幼稚園では、附属小学校・中学校への連絡進学制度が整備されており、多くの園児が継続した教育環境で成長を続けています。
幼稚園から中学校まで一貫した教育方針のもとで、お子さんの個性と発達段階に応じたきめ細やかな指導を受けられるでしょう。
内部進学により小学校受験の負担を軽減できるため、幼児期の貴重な時間を豊かな体験活動に充てられます。
\直前でも自宅で対策OK!/
今すぐ始める3つのアクション


弘前大学教育学部附属幼稚園の受験準備は、現在のお子さんの状況把握から始まります。
令和8年度の募集日程も確定し、準備の本格化が必要な時期です。
適切な情報収集と計画的な取り組みで、合格に向けた道筋を明確にしましょう。
【Step1】年齢別チェックリストで現在地を確認
お子さんの現在の発達状況を客観的に把握し、受験までの準備計画を立てましょう。
月齢に応じた発達目標と照らし合わせ、優先して取り組むべき課題を明確にしてください。
弘前大学教育学部附属幼稚園では「チューリップクラブ」の子育て支援事業を年7回実施しており、1歳〜就学前のお子さんが参加できます。
園の雰囲気を直接体験できる貴重な機会のため、積極的に参加して園生活への適応度を確認することが大切です。
語彙数・文章力・基本運動・手先の器用さを年齢基準と比較し、強みと弱みを把握します。
【Step2】園開放・説明会の申込み
園の雰囲気や教育方針を直接確認できる貴重な機会です。
早めの情報収集と申込みで、お子さんに最適な園選びを実現しましょう。
令和8年度の重要日程は、出願書類受付が9月2日〜19日、入園願書交付が9月24日〜10月3日に確定しています。
チューリップクラブは2週間前から受付開始のため、開催日程を事前に確認して申込みを行います。
園見学では教育方針の確認・施設環境・先生の対応を重点的にチェックし、お子さんの園の雰囲気への反応も判断材料として活用してください。
【Step3】最新情報の継続的な収集体制を整備
受験情報は日々変化するため、継続的な情報収集体制の構築が欠かせません。
信頼できる情報源を確保し、変更に迅速に対応できる仕組みを作りましょう。
公式情報を定期的に確認し、募集要項・選考方法・日程変更への迅速な対応準備をしておきます。
弘前大学教育学部附属幼稚園は通園区域が片道1時間以内に制限され、預かり保育も実施されていません。共
働き家庭では、保護者送迎義務に対応できる家族サポート体制を早急に整備し、勤務調整の準備も進める必要があります。
\直前でも自宅で対策OK!/
まとめ
弘前大学教育学部附属幼稚園の受験は、年齢別の段階的な準備で合格を目指せます。
通園区域制限や預かり保育未実施など厳しい条件がありますが、自由保育の教育方針と内部進学制度の魅力は大きいでしょう。
令和8年度の募集要項が確定し、3歳児30名・4歳児20名程度の募集が発表されました。
チューリップクラブへの参加で園体験を積み、共働き家庭は送迎体制の整備が欠かせません。
今から計画的な準備を始めれば、お子さんにとって最適な教育環境を手に入れられるはずです。
弘前大学教育学部附属幼稚園に向けた準備サポート
お子さんの自主性と考える力を育てるため、家庭学習の補助として通信教育や幼児教室を検討するご家庭も多くいらっしゃいます。
園の教育方針に合った教材選びで、お子さんの個性をさらに伸ばしてあげましょう。
考える力を育てる通信教育
「モコモコゼミ」(思考力重視の幼児教材)
こぐま会とSAPIXが監修する幼児向け通信教育で、暗記ではなく「考える力」を重視した構成が特徴です。
お子さんが自分で試行錯誤しながら答えにたどり着く体験を大切にしており、附属幼稚園が目指す「自らの課題を解決していこうとする力」の土台作りに役立ちます。